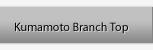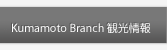|
茶臼山全体を要塞化した名城・熊本城 |
| 現在の熊本城(写真左は宇土櫓)は、加藤清正が築いたもので、茶臼山全体を要塞化した城である。しかしその堅固な名城も、明治10年に西南戦争勃発の折、残念ながら焼失してしまった。(石垣、櫓の一部はそのままの状態で、当時の全景写真も残されている。) |
|
 |
熊本県立美術館と二の丸公園 |
| 熊本県立美術館は、熊本城の二の丸公園の西側に隣接し、古代装飾古墳のレプリカ(常時観覧可)や現代美術などを展示している。同館は、昭和51年3月に開館した総合美術館。催し物としては、企画展、共催展、貸会場展など多彩な展覧会などを定期的に開催している。また、平成4年10月には、元県立図書館を分館としてリニューアルオープンした。 |
|
 |
旧細川刑部邸と熊本博物館 |
| 細川刑部邸は、現在熊本城三の丸内に移築復元されているが、当時肥後に入った第3代細川忠利公の弟・刑部少輔興孝が1646年に2万5千石を与えられて興したもの。鉄砲蔵を付設した長屋門に入ると、唐破風屋根の玄関から母屋で、客間、書院となっており、奥には「春松閣」と呼ばれる2階建ての銀の間がある。別棟は台所、茶室「観川亭」や書斎などがある大名一門の屋敷。一見の価値ある建物だ。 |
|
 |
夏目漱石旧居 |
| 明治29年、夏目漱石が今の熊本大学である第五高等学校の英語の教師となり、4年5ヶ月在住し、その間に6件の家に住んだ3番目の家。もともとは大江に在ったこの家から玉名郡天水町の小天(おあま)温泉への旅に出かけ、その経験を題材にして『草枕』が生まれたそうです。 |
|
 |
小泉八雲旧居 |
| 小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が松江から第五高等中学校の教師として熊本に赴任したのは、漱石より4年半前の明治24年(1891)11月19日のこと。熊本に到着した八雲は、それから数日間は借家を探すために不知火館(後の研屋支店)に宿泊し、手取本町34番地(鶴屋裏)赤星晋策氏の家を借家として探し当てた。八雲は新居に神棚を特注し、毎朝その神棚に拍手・礼拝して学校に通っていたと言われる。当時の八雲の生活環境は、殆ど日本式の畳の上の生活であったようだ。 |
|
 |
水前寺成趣園 |
| 水前寺成趣園は以前は修学旅行の定番であった。関西、関東方面からの修学旅行バスが連なり、熊本城見学のあと必ずと言ってよいほど同園に足を運んでいた。ロゼッタ・ストーンの月例クイズ応募者からも「阿蘇から熊本城、水前寺公園に行った事を思い出します。大変懐かしい!」といったメッセージが入ってくる。最近はめっきり減ってしまった修学旅行だが、熊本の歴史探訪などをテーマに、体験型の教育旅行地として復帰して脚光を浴びてもらいたいものである。 |
|
 |
徳富記念園 |
| 徳富旧居と徳富記念館 徳富記念園は、「徳富旧居」と明治100年事業として建築された「徳富記念館」を併せた名称。若干20歳の蘇峰が、明治15年に開いた大江義塾跡としても知られている。同園には蘇峰が師と仰いでいた新島讓が贈ったアメリカ土産(一粒の種)から大きく育ったカタルパの木が、今はその2代目・3代目として100年以上もの間、5月頃には真っ白な花をつけて園内を彩っている。 |
|
 |
加藤清正と本妙寺 |
| 「本妙寺宝物館」は、本妙寺境内にあり、熊本城の建造した名将・加藤清正(ニックネームは、清正公さん=セイショウコウサンと呼ぶ)の遺品や、加藤家や細川家に関する文書、書画、工芸品など約1400点が収蔵、展示されている歴史博物館。 |
|
 |
雲巌禅寺と五百羅漢 |
| 本妙寺から峠の茶屋を通り金峰山の西麓へ足を運ぶと、南北朝時代に日本に渡来した元の禅僧東陵永が開基したと伝えられる雲巌禅寺(曹洞宗に属する寺)という寺がある。
それは樹木におおわれ、神秘的な霊場として知られている寺である。岩山を削ってつくられた細道を通って行くと、右手に大きな岩盤(1枚岩)が見え、滑稽というか、不気味という表現が適切なのか分からないが、五百羅漢の幾体もの姿に圧倒されてしまう。すべての表情、姿の異なる沢山の羅漢が急斜面に座しており、沢山の顔々が一堂に視線を向けて来る。・・・自分に似た顔がどこかにありそうな。 |
|
 |
武蔵塚公園/宮本武蔵 |
| 門をくぐると宮本武蔵の二天一流「五方の形」の一つである『右直の構え』をした銅像が大樹の陰に立っている。その他、園内に清靖亭などがあり、その庭園奥には武蔵が眠る。この静かな庭園は毎年春に花見で賑わっている。 |
|