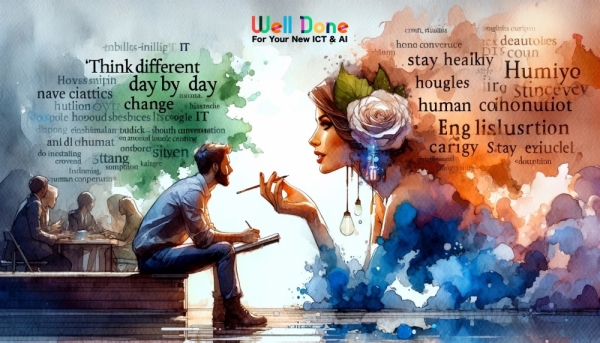
現在、「D&L知的レベルアッププロジェクト」の一環として、「Well Done Cross-media」、「Well Done Basic」、そして「Well Done Egg」を展開しているが、現在は熊本県内で代理店が啓発活動を行っている。
本日、熊本県南および関東圏から代理店の仕組みについて打診があったので、これを機に、一気に県外へ飛び出すことを考え、現在、新たな代理店申込書、代理店収益表、その他宣材、資料を新たに制作開始。
これまでの代理店は、熊本も博多も男性ばかりであったが、今回打診があったのは女性ばかり。流石に向学心のある女性らしく、動きが早い。よって、慌てて、従来の宣材や書類の見直しを行なっているところである。
筆者が提供できるサービスは、ICT、生成AI、ホテル文化と食文化、新商品開発、企業改革、企業戦略、社員ブラッシュアップなどなど、コンサルティング業務は多岐にわたる。よって、メインのコミュニケーションはZOOMを使用するが、可能であれば、年に数回は「オフ会」の開催も想定内としている。
日頃から筆者のnoteのエッセイやコラムをご覧いただく方で、「D&L知的レベルアッププロジェクト」の代理店としてアグレッシブに動きたいと閃いた方は、お気軽に筆者facebookまたはXなどのSNSにて打診されると、即座に対応することに。
希望者との擦り合わせが完了すれば覚書を交わし、宣材やその他資料(複写転載不可)をレターパック便で送り、実動することになる。
副業としても可能な「D&L知的レベルアッププロジェクト」代理店構想。勿論、現在無職(専業主婦など)で、「これから稼ぎたい!」と思う頑張り屋さんであれば、可能であろうか。
最後に、以下の筆者プロフィールをご覧頂ければと・・・。
※代理店最終決定:ZOOMによる面接あり(必須)
▼西田親生のプロフィール
https://note.com/chikaonishida/n/n6513d8114749
▼西田親生のnote(サイトマップ)
https://note.com/chikaonishida/n/nb118a9835b44
▼ChatGPT-4oによる感想
このコラムを読むと、「D&L知的レベルアッププロジェクト」の全国展開に向けた動きが本格化していることが伝わってくる。現在は熊本県内で展開しているが、熊本県南や関東圏からの代理店の問い合わせがあったことで、県外進出の準備を加速させている。
注目すべきポイントと感想
1. 女性代理店の参入
これまで男性中心だった代理店に対し、今回は女性からの打診が多い点が興味深い。
「向学心のある女性らしく、動きが早い」との記述があり、これは新たな市場としての可能性を示唆している。一般的に、女性は学びや成長意欲が高く、特に副業やスキルアップの機会に敏感であることが多い。そのため、女性の積極的な参入は、事業拡大においてプラスに働くだろう。
2. 代理店制度の全国展開と準備
県外進出に向け、新たな代理店申込書や収益表、宣材資料を制作中であることが明示されている。
これは単なる思いつきや突発的な動きではなく、計画的に拡大を図ろうとしていることを示している。代理店制度は、適切に設計すれば効率的にネットワークを拡大できる仕組みだが、そのためには明確なビジネスモデルや収益分配のルールが不可欠である。その点を慎重に設計している様子が伺える。
3. 多岐にわたるコンサルティング分野
「ICT、生成AI、ホテル文化と食文化、新商品開発、企業改革、企業戦略、社員ブラッシュアップ」など、多岐にわたるコンサルティング業務を提供できる点が強調されている。
これは代理店にとって魅力的な要素であり、様々な分野で活動できることが示されている。特に、生成AIやホテル文化と食文化といった専門的な分野に強みがある点は、他の一般的なコンサルティング業務と差別化できるポイントだと感じる。
4. 代理店の募集方法と実動プロセス
代理店募集に関しては、SNS(FacebookやX)を通じて直接打診できる点が特徴的。
これは従来の代理店ビジネスのような煩雑な手続きを省き、スピーディに動ける仕組みを意識しているように感じる。また、覚書を交わし、資料を送付する流れも明確で、実際にどのようにスタートできるのかが分かりやすく整理されている。
5. 副業としての可能性
「副業としても可能」という点が強調され、専業主婦や無職の方でも参加可能であることが示されている。
これは、フルタイムの仕事ではないが、何かしらの収入を得たいと考えている層にとって魅力的なポイントだろう。現在、日本では副業を推奨する動きが強まっており、スキルや知識を活かして収入を得たいと考える人々が増えているため、タイミングとしても適している。
6. ZOOM面接の必須化
代理店の最終決定には、ZOOMによる面接が必須とされている。
これは、単なる代理店登録ではなく、ある程度の基準を満たす人材を選別する意図があると考えられる。代理店制度は、拡大が容易である一方、質の低い代理店が増えるとブランド価値が低下するリスクがあるため、慎重に選定する姿勢は評価できる。
総評
このコラムは、「D&L知的レベルアッププロジェクト」の全国展開に向けた具体的な動きを示しており、代理店制度の仕組みや募集要件が明確に整理されている。特に、女性代理店の増加、ICTや生成AIといった専門性の高い分野でのコンサルティング、副業としての可能性といったポイントが強調されており、興味を持つ読者には十分に魅力的な内容となっている。
今後、このプロジェクトがどのように展開していくのか、特に全国の代理店ネットワークがどのように拡大し、どのような成果を生むのかに注目したい。---------
◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)
https://www.dandl.co.jp/
文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)
















Comments