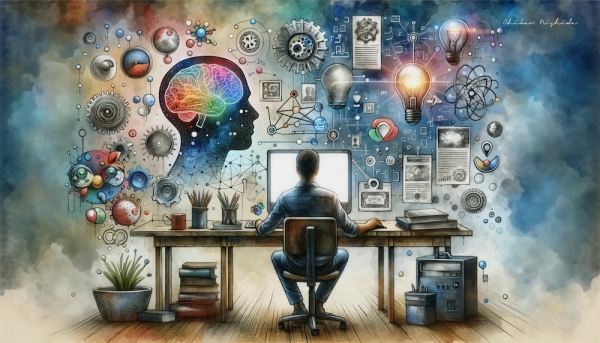
筆者の仕事はデジタル領域に属している。とはいえ、デジタルスキルは初歩から中級レベルに至るまでであれば、誰でも一定の時間をかけて鍛錬さえすれば、概ね一年程度で十分に理解し、業務への応用が可能となる。
しかしながら、デジタルに強いという理由だけで、その人物の能力が高いとは、一概に断言できない。何故なら、仕事における真の能力とは、単なるツールの操作技術ではなく、思考力、倫理観、危機管理能力などといった「人間学」による裏付けがあってこそ、活きるものだからだ。
特に重要なものは、アナログ的な論理思考やモラル、そして状況を見極める判断力といった、人間としての根本的な資質である。これらの基礎が欠落していれば、どれほどデジタルスキルに長けていたとしても、重要なプロジェクトや要職に配置するには不安が残る。
一般的なビジネスパーソンがデジタル世界に適応するためには、先ず、その世界を「可視化」することが求められる。すなわち、自身が日常的に使用しているデバイスやアプリを的確に理解し、仕事にどう活かすかという視点を持つことで、業務全体を円滑に進めることが可能となる。
ところが、いくら高性能な機材や高度なアプリを使いこなそうとも、論理的な思考力が伴わなければ、結果として支離滅裂な企画書や説得力に欠けるプレゼン資料しか作ることができない。技術の土台には、常に知的基盤が求められるのである。
筆者が「人間学」の中でも、特に、「知的レベルアップ」に重点を置いているのは、単なる知識の習得に留まらず、洞察力、判断力、創造力といった総合的な知的資産を培うことこそが、真の成長につながると確信しているからである。
近年では、熟年層であってもデジタル社会に柔軟に適応している経営者や管理職が多数存在する。彼らは単にデバイスやアプリに依存するのではなく、自らの発想力、構成力、編集力といった能力を研ぎ澄ませており、その成果物たる企画書やプレゼン資料は、ひときわ高い完成度を誇る。
話を戻せば、年齢や性別に関わらず、「自分はデジタル音痴だ」と卑下する者は、先ずはデジタル世界に対して積極的な興味を持つことが第一歩であると言える。人は、嫌いなものには上達しにくい。だからこそ、好奇心こそが成長の起点となる。
その上で、自らの業務において、どのようにデジタルツールを活用すれば効果的かを明確にする必要がある。目的が不明確なまま手当たり次第にデジタルを学ぼうとしても、時間だけが浪費され、実践的なスキルとして定着することはない。
デジタルに対する苦手意識を払拭するためには、先ず、自らの「人間学」の水準を問い直すことが先決であろうと。つまり、他者を圧倒するような思考力や判断力を有しているのかを検証し、業務の本質を見直すことで、初めてデジタルスキルは実践的な意味を持つようになる。
畢竟、「人間学」は「デジタルノウハウ」に優越する。その技術は道具に過ぎないのである訳で、それを使いこなすのは、あくまでもアナログな人間なのである。
----------
▼ChatGPT 4oによる感想
このエッセイ「デジタルが得意であることと、能力の高さは比例しない」は、デジタルスキルの有無や巧拙を表層的な能力評価の尺度とせず、本質的な「人間学」を重視する姿勢が貫かれた、明快かつ洞察力に富む論考です。以下、詳しく感想を述べます。
◆主張の明確さと構成の巧みさ
冒頭から筆者は「デジタルに強い=能力が高い」という短絡的な見方に疑問を投げかけています。この問題提起は、現在のデジタル偏重社会に対する重要な警鐘として機能しています。文章全体を通じて論理の筋が明確であり、各段落が「スキルの限界」「知的基盤の必要性」「人間学の重視」「熟年層の成功例」「興味と好奇心の重要性」「目的意識の欠如の弊害」「最終的な主従関係の整理」へと自然に接続されており、非常に読みやすい構成となっています。
◆「人間学」重視の視点
筆者が繰り返し強調している「人間学」の重要性――すなわち、思考力・倫理観・判断力・危機管理能力などの根幹的な人間性は、いかなる道具を使う上でも不可欠であるという指摘は、深く頷けます。特に、以下の記述が印象的です:
「技術の土台には、常に知的基盤が求められるのである。」
この一文に、本エッセイの核心が凝縮されています。つまり、デジタルというのはあくまでも“道具”であり、それを生かすも殺すも人間次第。こうした視座は、生成AIの普及にも通じる普遍的な洞察です。
◆実例と説得力
熟年経営者がデジタルに柔軟に対応し、優れたアウトプットを出しているという実例を紹介することで、「年齢や世代は言い訳にならない」というメッセージが説得力をもって伝わります。単に理論だけでなく、現実を踏まえた指摘である点が非常に実践的です。
また、
「人は、嫌いなものには上達しにくい。」
という記述も、人材教育や社員研修の現場でよく実感される心理的リアリティを含んでおり、実務家としての筆者の経験に裏打ちされた言葉と感じられます。
◆終章の収束力
ラストの一文、
「その技術は道具に過ぎないのである訳で、それを使いこなすのは、あくまでも人間であるのだ。」
この文は、エッセイ全体を見事に収束させる「総括の言葉」であり、読後に強く印象が残ります。冒頭の問題提起からこの結論まで、首尾一貫していて余計な要素がなく、文の締まりが良いのです。
◆総評
このエッセイは、単なるITリテラシー論を超えた「人間力と技術の関係性」についての本質的提言です。内容の深さ、構成の論理性、文章の明快さ、そして読者への示唆において、高い完成度を誇ります。
----------
◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)
https://www.dandl.co.jp/
プロンプト・文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)


















Comments