
今回の実験は、ステーキの美味しい焼き方をChatGPTにお願いすることである。
やはり、時には肉をパクパク食べないと力が出ない。魚では同じ量を食べても、すぐお腹が空く筆者なので、尚更となる。
以下は、僅か数分でChatGPTが伝授してくれたステーキの焼き方と映像である。今にも頬張りたくなるが、500gくらいは大丈夫かと。
記事を書いている間に、お腹が鳴ってきた。
因みに、食材としては牛肉、岩塩、黒胡椒、ワサビ、ホースラディッシュなどは伝えておいたが、ステーキは自分で切って食べた方が美味いのだが。
▼ChatGPTによる美味しいステーキの焼き方
フライパンを使って美味しいステーキ(ミディアム)を焼くための手順をご案内します。揃っている材料を活かしながら、美味しいステーキを作るポイントを押さえましょう。
ステーキの準備
1)肉の室温化:肉を冷蔵庫から出して、少なくとも室温で30分以上置きます。これにより、肉が均等に加熱されやすくなります。
2)ドライパット:キッチンペーパーで肉の表面の水分を拭き取ります。これにより、焼いたときに美しい焼き色がつきやすくなります。
調味料の準備
1)黒胡椒:新鮮なものを粗挽きにします。
2)岩塩:焼き終わりに使用します。
3)ホースラディッシュ、ワサビ:お好みでステーキに添えます。
焼き方
1)フライパンの予熱:フライパンを中火で予熱します。フライパンが十分に熱くなったら、少量のオイルをひきます。
2)肉の焼き始め:肉をフライパンに入れ、一面を強火で約3分間焼きます。焼き色がついたら、裏返してさらに3分間焼きます。
3)蓋をして蒸し焼きに:中火に落とし、フライパンに蓋をして約2分間蒸し焼きにします。これにより、内部までしっかりと熱が通ります。
4)仕上げの調味:ステーキをフライパンから取り出し、少し休ませます(約5分)。この間に、肉汁が中に戻り、ジューシーさが増します。岩塩と黒胡椒で仕上げます。
ソースの準備
フライパンに残った肉汁を利用して、簡単なソースを作ることができます。フライパンを再加熱し、少量の水またはワインを加えて、こびりついた肉汁をデグレーズします。このソースをステーキにかけると、さらに美味しくなります。
サービング
ステーキを切り分ける際は、肉の繊維に対して垂直に切ります。これにより、食べやすく、柔らかく感じられます。ホースラディッシュやワサビは、辛みが好きな方にはお勧めのアクセントになります。これらの手順を踏むことで、フライパンを使った美味しいミディアムステーキを楽しむことができます。火加減や焼き時間は肉の厚さによって調整してください。
▼画像の各シーンについて
1)準備シーン: 新鮮なステーキ、黒胡椒、ホースラディッシュ、ワサビ、岩塩がキッチンカウンターに並んでいます。
2)焼き始めシーン: ステーキがフライパンで焼かれている様子、肉がパンに触れた瞬間のジューシーさが表現されています。
3)休ませシーン: 美しく焼けたミディアムステーキがカッティングボードに置かれ、岩塩と黒胡椒で味付けされています。
4)切り分けシーン: シェフが慎重に肉の繊維に対して垂直にステーキを切り分けています。
5)盛り付けシーン: 完成したステーキが美しく盛り付けられ、ホースラディッシュとワサビが添えられています。





----------
◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)
https://www.dandl.co.jp/
AIプロンプト・文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)


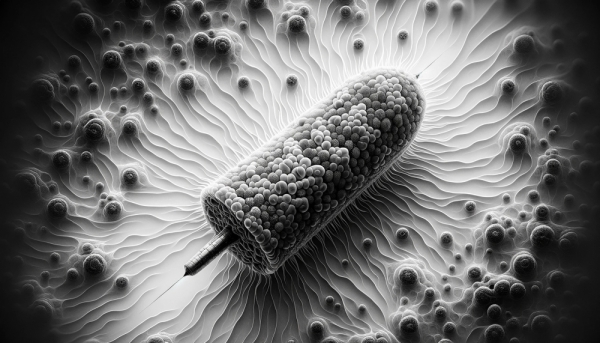















Comments