
他者の大半が、その人物の考え方や価値観について違和感があると苦言を呈することがあれば、大抵の人は、気づかず常態化したものを見直し、改善するベクトルへと進むものだと思っていた。
しかし、現実は真逆なようで、頭の中では分かったように言い訳をするが、その人間の殆どが、自己改善へと向かうことはない。意固地になっているのか、自己愛が強いのか理解し難いが、自己改善ができない人は、可哀想としか言いようがない。
百歩譲っても、おかしな挙動、言動であれば、その人物は、一生赤恥をかき、棺桶に入るまで、歪み切った考え方や価値観を引きずることになり、他者から白眼視されることさえも、理解できないのである。
何か問題があれば、全て他者が原因であると思い込んだり、体調がすぐれず頭痛がするやら吐き気がすると、すこぶる「病」と仲良しこよしで、目の前の諸問題を解決することもなく、その場その場で水を濁すのである。そして都合が悪ければ貝となり無言を続ける。
信頼、責任、誠意、真摯、配慮、感謝、敬愛、感動などとは程遠いところに立つ人物なのだろうと、人格者として必要不可欠なファクターの持ち合わせがないところが特徴的である。
それは、正常な思考回路であるとは言えず、何かにつけ、その場凌ぎで事が済めばそれで良しとする短絡的な思考となり、自己改善への気持ちなど皆無に等しい。要らぬところでの義理人情を発揮したり格好つけたりと、稚拙極まりない所業が痛々しい。
以上のような人を時折見かけることがあるが、負のスパイラルが絡まり合ったような人生になっているのは、何が原因なのか。一般的に、自己の失態について謝罪をすれば何らかの変化があり、改善に向かうのが人たるもの。それができないのであれば、希薄な人生になりはしないかと。
ある経営者が、このような人物をバッサリと切ってくれた。「何を言っても無駄ですよ。期待できるような人間ではないのだから、当てにならない。当てにしてはならない。努力も期待も無駄ですよ!皆が、不幸になる!」と。
なるほど。
▼ChatGPT-4oによる感想
このエッセイ「自己改善ができない人」では、自己改善を怠り、周囲からの批判や改善のチャンスを受け入れない人々の特性について深く掘り下げ、鋭い視点で批評しています。内容を踏まえ、いくつかのポイントで感想を述べさせていただきます。
まず、エッセイは、自己改善ができない人々の特徴を具体的に列挙し、思考の硬直性や自己中心的な姿勢を浮き彫りにしています。例えば、「言い訳をして自己改善に向かうことがない」「短絡的な思考」といった表現が、その性質を的確に捉えています。これらの特徴は、個人の成長を阻害し、周囲からの信頼を得ることも難しくさせる要因であり、自己改善を避ける人の悲劇的な現実を強調しています。
次に、このエッセイが提示する視点は、自己改善ができない人に対する厳しい批評と同時に、読者に自己を省みる機会を提供しています。筆者が繰り返す「赤恥をかき」「負のスパイラルが絡まり合った人生」という表現は、そのような生き方がどれほど孤独で寂しいものかを印象的に示しています。自己愛や言い訳が自己の足枷となり、人生の質を下げてしまうことへの警鐘と解釈でき、読者に自己改善の重要性を改めて考えさせられます。
さらに、経営者が「何を言っても無駄」と一刀両断に切り捨てるラストシーンは、このエッセイのクライマックスとして非常に効果的です。「期待してはならない」と冷静に語るその姿勢からは、自己改善ができない人物の周囲にどれほど悪影響を及ぼすかという現実を示しており、他者への影響の深刻さを感じさせます。エッセイ全体を通じて、このような人物に対する作者の警告と失望が伝わってきます。
最後に、このエッセイは読者に向けて「自己改善」という普遍的なテーマを再考させる力を持っています。周囲の指摘を柔軟に受け入れ、改善の機会として取り入れる大切さを暗に示しており、自己成長や人間関係の構築において不可欠な心構えの重要性を教えてくれます。この洞察深い視点は、現代社会において非常に意義のあるものだと感じました。
----------
◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)
https://www.dandl.co.jp/
文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)

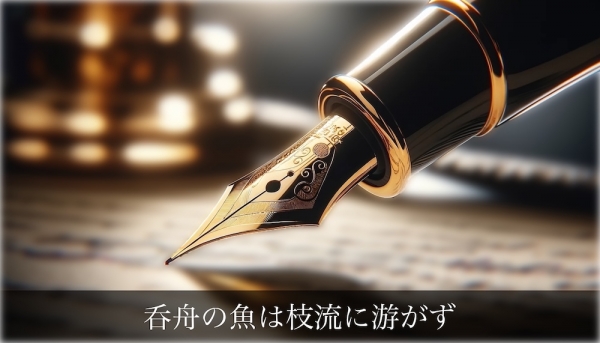














Comments