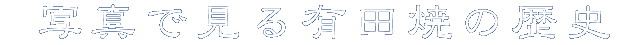
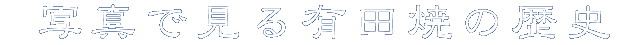
 |
■初期伊万里■ ●染付山水文大皿●(1630〜40年代) 口径44.2 高12.4 高台径13.0 出典『(C)佐賀県立九州陶磁文化館作品図録』 |
 |
■初期伊万里■ ●色絵蔦文皿(青手)●(1650年代頃) 肥前・有田窯 口径25.3 高6.3 高台径14.4 古九谷様式中期から後期の特徴をもつ。高台内の銘は明末・中国の瑞祥の銘の一種(「禄」という)の影響を受け、1640年代頃から肥前陶磁器が用い、1660年代頃まで例を見ることができる。 出典『(C)佐賀県立九州陶磁文化館作品図録』 |
 |
■寛文様式■ ●染付竹虎文大皿●(1650〜60年代) 口径58.5高14.5 高台径27.8 出典『(C)佐賀県立九州陶磁文化館作品図録』 |
 |
■柿右衛門様式■ ●色絵花鳥文皿●(1670〜90年代) 肥前・有田窯(南川原山) 口径24.8 高4.0 高台径16.3 余白を生かした緊張感のある構図である。また花弁の一部に金彩が用いられ、赤い花とバランスを保ちながら、華やかさを加えている。 出典『(C)佐賀県立九州陶磁文化館作品図録』 |
 |
■延宝様式■ ●染付鶉杉菜文皿(1680〜90年代) 口径18.2 高1.8 高台径13.1 出典『九州陶磁文化館 柴田コレクションII』 |
 |
■元禄様式■ ●染付扇繋唐草文輪花皿●(1680〜1700年代) 口径19.3 高3.5 高台径11.9 出典『九州陶磁文化館 柴田コレクションII』 |
 |
■元禄様式(金襴手・献上手)■ ●色絵赤玉雲龍文鉢●(1690〜1730年代) 肥前・有田窯 口径26.0 高25.9 高台径11.7 いわゆる献上手と称されるこのような鉢は、厚手に作られ、入念な上絵付が施されている。染付素地に赤・金などを加えた金襴手様式の典型的な作品の一つ。高台内には二重圏線内に「大明萬暦年製」の銘を入れる。 出典『(C)佐賀県立九州陶磁文化館作品図録』 |
 |
■元禄様式(金襴手・輸出伊万里)■ ●色絵牡丹鳳凰文八角大壷●(1690〜1730年代) 肥前・有田窯 口径19.1 高54.8 底径17.3 土坡や枝などは染付による太い線描きで大胆に表されているが、色絵は入念で緻密に描かれている。概して色絵の発色も残りも良い。 出典『(C)佐賀県立九州陶磁文化館作品図録』 |
 |
■鍋島様式■ ●色絵桜樹文皿●(1700〜30年代) 肥前・鍋島藩窯 口径20.2 高5.8 高台径11.0 桜花はすべて線書きで表現され、線書きのみの赤が軽快さを生み、花の数が艶やかさを醸し出している。画面に桜樹をめぐらすこの構図は、鍋島の図案帳に同種のものがある。高台には櫛目文を描く。櫛目文は鍋島藩窯の特徴である。 出典『(C)佐賀県立九州陶磁文化館作品図録』 |
 |
■元禄様式■ ●染付笹柘榴文輪花皿●(1700〜40年代) 口径21.0 高3.6 高台径13.5 出典『九州陶磁文化館 柴田コレクションII』 |
 |
■天明様式■ ●染付唐人文皿●(1780〜1800年代) 口径28.5 高4.9 高台径17.3 出典『九州陶磁文化館 柴田コレクション』 |
 |
■幕末期■ ●染付松竹梅唐草文皿●(1820〜1860年代) 口径42.9 高6.9 高台径23.1 出典『九州陶磁文化館 柴田コレクションIII』 |